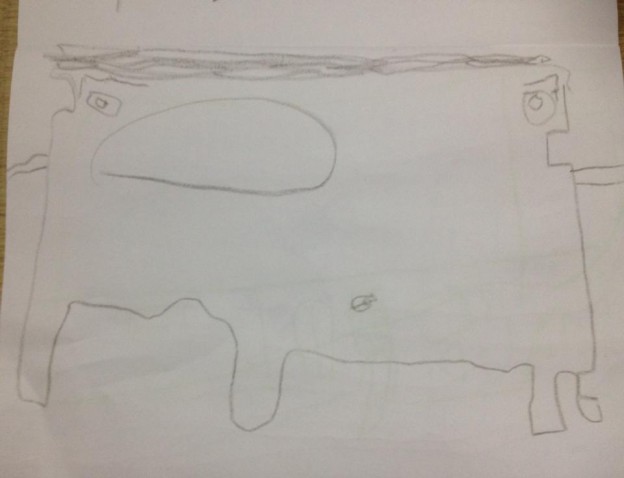3歳9ヶ月の息子は、きたる進級に強い想いをはせているようだ。「今度○○○組になる?」と連日聞いてくる。
成長というのは、日々起こる。今日、保育園から帰るとき、バス停で「お家に帰ったら人を描く」と言い始めた。「人って誰?お父さんの絵を描いてくれるん?」と聞いてみると、うんと言う。嬉しくなってくる。帰宅するとちゃんと描いてくれた。シュールだ。でも、きっとこれが僕なのだろう。普段描いているバスの絵と本物のバスと、その違いを頭に入れながら見ると、やはりこれは僕だ。かつて息子が初めて寝返りをうてるようになった時、初めて足で立てた時、初めて言葉を発した時。そういう明確な成長の陰にある、成功には至らない成長。日々、彼は成長している。だがそういう日々の成長はあまりに緩やかで、自分自身でさえそこに成長があるということに気づくのは難しいのではないだろうか。そう思う。
そういう中、卒業とか、資格取得とか、なんらかの看板が成長に気づくためのマイルストーンになるというのなら、その効用も認めざるを得ない。それは単なる一里塚に過ぎず、そこに至る一歩一歩に貴重な何かがあると知りつつも、一里塚に辿り着いた時にしか確認できない何かというものもある。息子が今いる●●組から○○○組に変わるということが、彼にとっての成長の印なのだろう。○○○組になったら、おクツを○○○組さんの靴箱に入れるのだと興奮して教えてくれる。その想いが自分の成長のガソリンになり、プライド的な何かになるのであれば、それも悪くないと思う。
その保育園にお迎えに行く途中の道で、帰途に着いた先生とすれ違う。軽く会釈をする。さようなら、お疲れさまです。その先生は今朝息子を送っていった時に外での立ち番をやっていて、園から出ていく僕に「お父さん、足だいぶ自然になってきてはりますね」と声をかけてくれた。その先生は年明けに名前が変わったと掲示されていた。結婚されたのだ。その日の帰りに息子を玄関まで連れてきてくれた時に「おめでとうございます」と声をかけると、「あ、名前覚えてくれてはったんですか〜」と嬉しそうに返事されていた。息子の担任の先生ではないので、覚えていないとしても不思議は無い。だが、いつも僕らがお迎えに行くと、外で立ち番している先生はみんな親の顔を見るだけで「○○ちゃん、お迎えです」とヘッドセットマイクを通じて園内に知らせてくれる。全学年の園児の名前を覚えるだけでもひと苦労だと思う。それを、全園児の両親の顔と名前を覚えなければならないのだ。当たり前のようにさらりとやってくれているが、大変なことだと思う。だから先生の名前を覚えるくらいは父兄として、いや毎日のように顔を接する人間として、やっておくべきことなんじゃないだろうか。春先に先生たちの顔写真と名前が10日くらい掲示板に貼り出されていたので、それをスマホで撮影して、顔と名前を一致させる。オッサンには人の名前を覚えることはけっこう高いハードルなのだが、頑張った。名前が変わると掲示されていた先生にお祝いの挨拶をでき、ちょっとだけだけども先生との距離が縮まったのは、その頑張りが役に立ったなという瞬間だった。
その先生も、今期をもって退職される。結婚を機のいわゆる寿退職ということだろう。結婚で仕事をやめることの是非とか、今話題の保育士の待遇問題とか、そういうことを考え始めると退職されることが良いことなのか良いことじゃないのかよくわからなくなってくるわけだが、しかし、僕は良いこととしてエールを送りたい。その先生だけではない。息子を昨年担任してくださった先生も2人お辞めになる。それ以外にも数人退職される。春は、出会いと別れの季節だ。それぞれにいろいろな事情があって道を決められているのだろう。日常が徐々に変わっていくものであっても、区切りというものはやはり必要で、先生たちひとりひとりの人生も、区切りをもって変わっていく。どうせ変わっていくのなら、新たな門出のその先に幸あれと願いたい。区切って、次に進むということは、とても大事なことなのだ。帰り道でのさようなら、お疲れさまでしたは、もしかするともう会うことも無いかもしれない先生への、この2年間の区切りでもあったような気がする。
毎日のように顔を合わせるのが当たり前だった人が、もう会うことも無くなるのかもしれないというのは、それも日常とはいえ、切ないものだなとあらためて感じる、そんな3月終わりである。